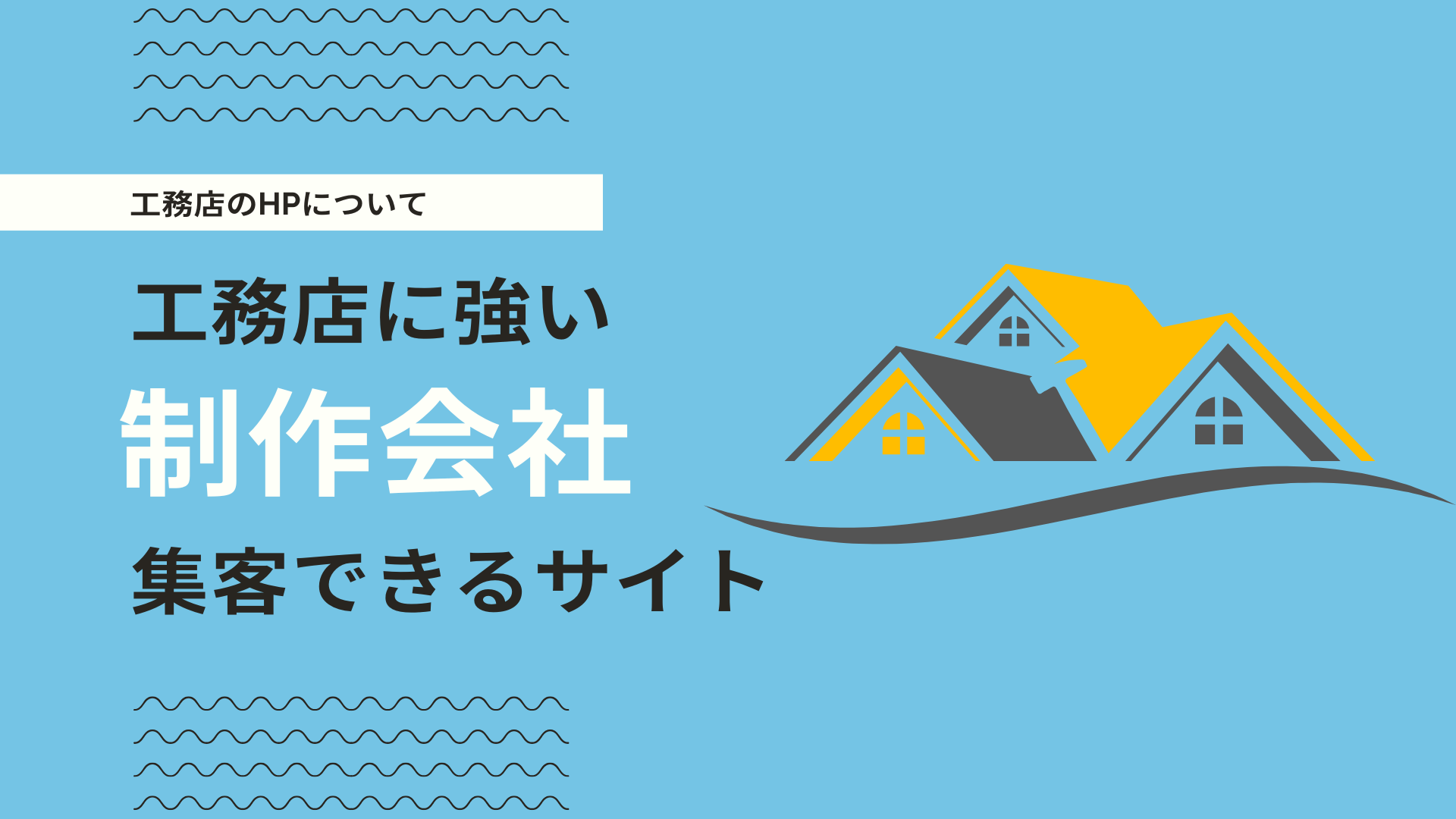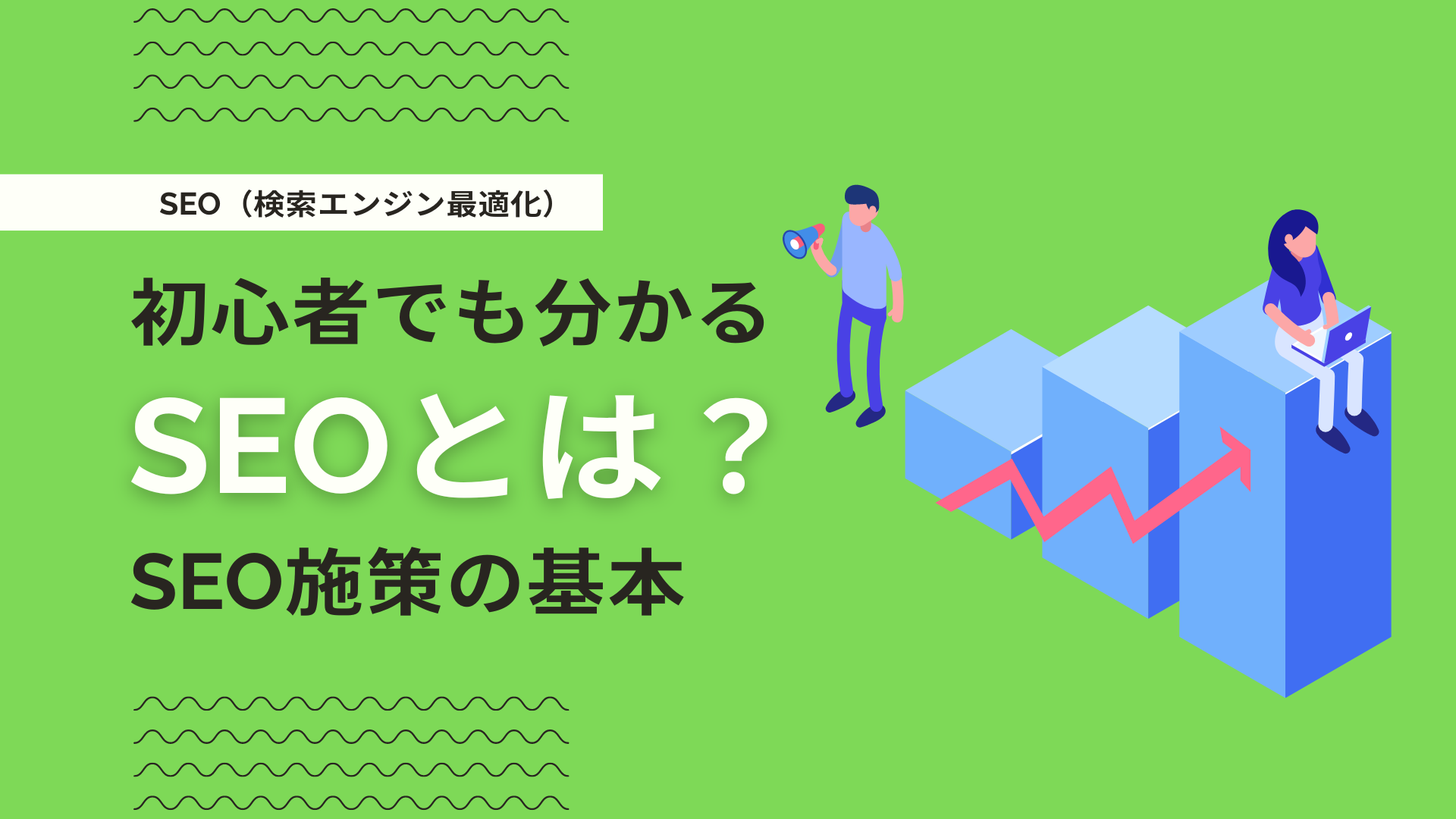ユーザー視点でサービスやプロダクトを設計したいとき、強力な手がかりとなるのが「ユーザーシナリオ」です。活用できれば非常に有効な手法ですが、作り方がわからない方も多いのではないでしょうか。
本記事では、ユーザーシナリオの基本から、準備・描写・改善の3ステップによる具体的な作成手順までを、実例を交えながらわかりやすく解説します。UX改善やチームでの共有に活かしたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
COOMIL(クーミル)株式会社 代表取締役。神奈川県出身。東京薬科大学大学院を修了後、大手製薬会社にて研修開発に従事する。2016年にファングロウス株式会社を創業し、マーケティング、広告運用、YouTube、SEO対策を駆使し、2年で売上1億円強かつ利益率40%強の会社へとグロースさせ、株式譲渡。YouTubeチャンネルのプロデュース・原稿制作・出演・撮影・編集の全てを自ら行い、運営10ヶ月で登録者数1万人突破させる(現在3万人越え)。IT業界だけでなく実店舗経営の知見を活かし、クライアント様の課題の本質を捉えて、「結果が出るマーケティング施策」をご提案致します。サイトを公開後も運用をお任せ頂き、サイトだけでなく「事業規模の拡大を目指す」ことがクーミルのモットーです。
■経歴
2014年 東京薬科大学大学院終了
2014年 第一三共株式会社
2016年 ファングロウス株式会社 創業
2019年 一般社団法人スーパースカルプ発毛協会(FC本部) 理事
2021年 ファングロウス株式会社 株式譲渡
2021年クーミル株式会社 創業
■得意領域
SEO対策
コンテンツマーケティング
リスティング広告
オウンドメディア運用
フランチャイズ加盟店開発、集客
■保有資格
Google アナリティクス認定資格(GAIQ)
Google 広告検索認定資格
Google 広告ディスプレイ認定資格
Google 広告モバイル認定資格
■SNS
X(旧Twitter):https://twitter.com/ryosuke_coomil
YouTube:https://www.youtube.com/@marketing_coomil
サイト改善の悩み
を無料で相談する
Step1
ありがとうございます
弊社にご相談頂きまして
誠にありがとうございます。
クーミル株式会社では、
1つ1つのご相談を真剣に考え、
最適解をご提供出来るよう日々努めております。
可能な限り、即日ご返信を心掛けておりますが、
相談内容や、
営業日の関係で少々、
お待たせさせてしまうかも知れません…。
目次
- ユーザーシナリオとは?
- ユーザーシナリオの具体例
- ユーザーシナリオを類似した施策について
- ユーザーシナリオとカスタマージャーニーとの違い
- ユーザーシナリオとユーザーストーリーの違い
- ユーザーシナリオとユースケースの違い
- ユーザーシナリオの作り方:準備
- プロジェクトの目的を明確にする
- ペルソナを設定する
- ユーザーシナリオの作り方:描写
- 行動のスタートとゴールを決める
- 行動プロセスを時系列で書き出す
- ユーザーの心理を描く
- ユーザーシナリオの作り方:改善
- シナリオ全体を見直し改善点を探す
- 改善策とアクションプランをまとめる
- ユーザーシナリオを作る4つのメリット
- 1.ユーザーの行動全体を一目で把握できる
- 2.潜在ニーズや感情を見つけやすくなる
- 3.課題や改善点を明確にできる
- 4.チーム全体でユーザー理解を共有できる
- まとめ
ユーザーシナリオとは?
ユーザーシナリオとは、ある製品やサービスに出会ったユーザーが、どのような状況でそれを知り、利用し、どう変化していくのかを描いたストーリーです。ユーザーの目的・行動・感情の流れを時系列で整理し、「いつ・どこで・なぜ・どんな気持ちで使うのか」を具体的に可視化します。

ユーザーシナリオの具体例
- 具体例:「海外出張が決まり、英語に自信がない…」
- ユーザーは仕事で英語を使う必要が出てきたが、英語力に不安を感じている。
- 具体例:「ネット検索で“短期間で英語を話せるアプリ”を発見」
- 「短期間 英語 学習 アプリ」などと検索し、口コミ評価が高い語学アプリを見つける。
- アプリの広告や知人の紹介を通じて知ることもある。
- 具体例:「通勤時間にアプリで英会話レッスン」
- 毎日スキマ時間を活用し、アプリでリスニングやスピーキング練習を続ける。
- クイズ形式で楽しく学べるので、飽きずに続けられる。
- 具体例:「英語会議で発言できるようになり自信がついた」
- 出張先で現地スタッフとスムーズにコミュニケーションでき、仕事の成果にもつながる。
- 自己肯定感が高まり、さらに別の言語学習にも意欲が出てくる。
| ステップ | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| ある状況 | 何かに困っている | 英語が話せない |
| 知る | 製品やサービスを知る | 語学アプリを発見 |
| 利用する | 使って体験する | 通勤中に英語学習 |
| 変化する | 効果を感じる・満足する | 英語で会議に参加できる |
上記のようにユーザーシナリオを構築することができると、単なる属性情報や行動履歴だけでなく、その背景にある感情や期待も含めて描くとより深いユーザー理解が可能です。
また、関係者間でユーザー理解を統一する際にも効果があります。抽象的なユーザー像ではなく具体的な状況と感情を共有できるため、プロジェクトの意思決定に一貫性を持たせることが可能です。
ユーザーシナリオを類似した施策について
ユーザーシナリオと似た施策として、以下の3つがあります。
- カスタマージャーニー
- ユーザーストーリー
- ユースケース
それぞれ目的や活用の場面は異なりますが、いずれもユーザー理解を深め、より良い体験設計を目指すためのアプローチです。
| 項目 | ユーザーシナリオ | カスタマージャーニー | ユーザーストーリー | ユースケース |
|---|---|---|---|---|
| 主な目的 | ユーザーの行動・心理を具体的に描写し、UXや設計に活かす | 顧客の体験を時系列で可視化し、タッチポイント全体を整理する | 要件定義や機能実装の方針を簡潔に示す | システムの仕様を明確にするため、操作と応答の流れを記述 |
| 対象範囲 | 特定の状況や利用シーン | 購入前から利用後までの全体的な体験フロー | 特定機能や目的に対する短い要望 | 機能単位での操作プロセスやシステムとのやりとり |
| 記述スタイル | 具体的な状況・行動・感情をストーリーとして描写 | フロー図や表形式など、視覚的にマップ化される | 「○○として、△△のために、□□したい」の形式で一文で記述 | ユーザーとシステムの動きを時系列に記述(例:UMLユースケース記法など) |
| 活用シーン | UX設計、マーケティング施策の検討、プロダクト改善 | カスタマー体験全体の分析や課題発見 | アジャイル開発における要件定義やタスク設計 | 要件定義、システム仕様のドキュメント化 |
| ユーザーの心理描写 | あり | あり | 基本なし | 基本なし |
| 技術的な詳細 | 含まない | 含まない | 含まない | 含む |
ユーザーシナリオとカスタマージャーニーとの違い
- ユーザーシナリオ:
「特定の場面におけるユーザーの行動や感情」を細かく描くもの - カスタマージャーニー:
「サービス全体に関わるユーザー体験の流れ」を整理するもの
ユーザーシナリオでは、ある状況下での心理や行動を物語形式で捉え、UX設計や機能改善に活かします。一方、カスタマージャーニーは、ユーザーが最初にサービスを知ってから購入・利用に至るまでの各段階を整理し、接点ごとの課題や改善点を明らかにする手法です。
具体例
- ユーザーシナリオ:
夜にスマートフォンで情報を探し、不安になりながら問い合わせページを開いた - カスタマージャーニー:
大学の入試情報ページを見直す場合、検索から閲覧、申込に至る一連の行動を時系列で整理
目的と使い方が異なるため、状況に応じて適切に使い分けることが重要です。
ユーザーシナリオとユーザーストーリーの違い
- ユーザーシナリオ:
「特定の場面におけるユーザーの行動や感情」を細かく描くもの - ユーザーストーリー:
「一文で簡潔に機能や要望」を示すもの
ユーザーストーリーは「○○として、△△のために、□□したい」の形式で書かれ、開発現場での機能共有や優先順位づけに用いられます。
具体例
- ユーザーシナリオ:
受験生がスマートフォンで大学の評判を調べ、不安を解消して資料請求をする(体験談) - ユーザーストーリー:
受験生として、不安を解消するために、卒業生の声を見られるようにしたい(簡潔にまとめる)
ユーザーシナリオとユースケースの違い
- ユーザーシナリオ:
人の感情や行動の背景を含めて体験全体を描き、UXや導線設計に活用する。 - ユースケース:
ユーザーの操作とそれに対するシステムの反応を時系列で整理し、機能要件の明確化を目的とする。
ユースケースの具体例
- ユースケース:
- 利用者が施設一覧を選択 → 条件で絞り込み → 入園申請フォームへ → 入力・送信 → 確認画面表示
上記のような操作の流れを記述します。
ユーザーシナリオの作り方:準備
ユーザーシナリオはいきなり描き始めるのではなく、事前に必要な準備を整える必要があります。まずはユーザーシナリオの作り方として、準備フェーズを見ていきましょう。
- プロジェクトの目的を明確にする
- ペルソナを設定する
プロジェクトの目的を明確にする
ユーザーシナリオを描く前に、プロジェクトの目的を明確に設定することが重要です。目的が定まっていないとユーザーに期待する行動や設計上の優先度が曖昧になるため、効果的なシナリオは作れません。目的例は以下のとおりです。
- 商品の購入数を増やす
- 離脱率を下げる
上記のように目指す成果を先に言語化すると、シナリオ内でユーザーがどのように行動すべきかがはっきりします。目標を定めておけばシナリオが感覚ではなく、成果に直結するロジックで構築できるはずです。
ペルソナを設定する
リアルなユーザー体験を描くには、想定読者のペルソナを具体的に設定する必要があります。ペルソナとはサービスの典型的な利用者像です。設定する際は、以下のような要素をできるだけ詳細に描き出します。
- 年齢
- 性別
- 職業
- 家族構成
- ライフスタイルや価値観
- 抱えている課題や悩み など
ペルソナ設定の具体例
30代女性/都心勤務/時短勤務中のワーキングマザー/小学生の子ども2人と夫と4人暮らし/平日夕方は家事と育児で忙しい/週末はネットショッピングを活用
上記のように、実在しそうなプロフィールを構築します。ペルソナが曖昧だと、行動や心理にリアリティが欠けてしまい、説得力のあるシナリオにはなりません。
ユーザーシナリオの作り方:描写
ユーザーシナリオの準備が整ったら、具体的な行動や心理の流れを描いていくフェーズに移ります。続いて、シナリオにリアリティを持たせるために必要な描写のプロセスを紹介します。
- 行動のスタートとゴールを決める
- 行動プロセスを時系列で書き出す
- ユーザー心理を描く
行動のスタートとゴールを決める
ユーザーの行動を描くには、出発点と目的地点を先に定める必要があります。スタートとゴールが明確でないと行動の途中過程が曖昧になり、説得力のあるシナリオが作れません。
- スタート → 英検対策を始めたいと思い、アプリをダウンロードする
- ゴール → 模擬試験で高得点を出し、自信を得る
上記のように行動の始まりと終わりを設定すると、シナリオ全体の軸が明確になります。行動の前提となる状況と、ユーザーが最終的に達成したい成果をはっきりさせましょう。
行動プロセスを時系列で書き出す
シナリオの軸が決まったら、ユーザーの具体的な行動を時系列に沿って整理します。流れに沿ってサービス内の操作や選択肢を細かく描くと、より現実に近い体験が再現されます。ここで重要なのは、一貫性と具体性を持って行動をつなげることです。
- 自宅でアプリを起動する
- リスニング教材を選ぶ
- 1日10分の練習を毎日継続する
- 結果を確認して次の課題を選ぶ
「アプリを使う」といった曖昧な表現ではなく、「いつ」「どこで」「どの機能を使ったか」までを具体的に書くと、より実態に近い体験が再現できます。
ユーザーの心理を描く
行動にリアリティを持たせるためには、ユーザーの心理状態や思考も合わせて描写します。表面的な動作だけではなく、背景にある動機や感情を補うとシナリオの精度が格段に上がります。
例えば、「忙しい高校生が短時間でも達成感を得たい」と考えている場合、以下のような心理描写が考えられます。
- 「10分以内で終わる教材を探す」
- 学習へのハードルを下げたいという思いが表れている
- 「短時間で終えられてホッとする」
- 忙しい中でも続けられたことに安心感を得ている
- 「毎日続けられている自分に満足する」
- 継続できた達成感が次の行動へのモチベーションになる
行動の裏にある感情や考えを具体的に補足すると、シナリオにリアリティと説得力が加わるはずです。
ユーザーシナリオの作り方:改善
ユーザーシナリオは描いて終わりではなく、定期的な見直しと改善が不可欠です。完成したシナリオをもとに改善点を探り、具体的なアクションに落とし込む手順を見ていきます。
- シナリオ全体を見直し、改善点を探す
- 改善策とアクションプランをまとめる
シナリオ全体を見直し改善点を探す
完成したシナリオを最初から読み返し、ユーザーの行動や心理に対して違和感や不自然さがないかを検証し、ボトルネックとなり得るポイントを明確にします。以下のような点に注目すると、見落としていた課題に気づけるでしょう。
- ユーザーが戸惑いそうな操作や選択肢がある
- 離脱が発生しやすい導線や画面遷移になっている
- 不安や迷いを引き起こすような情報不足や曖昧な表現がある
例えば「ログイン後に何をすればいいかわからない」といった状態が発生していれば、ナビゲーションやガイドの改善が必要です。シナリオ内の不明瞭な点をひとつひとつ解消すると、体験全体の質を高められます。
改善策とアクションプランをまとめる
見つかった改善点に対して、実行可能な対策を整理しましょう。解決の難易度や影響度を判断し、優先順位を設定することがポイントです。
例えば、「導線が複雑で離脱が多い」場合は、操作数の削減やステップの再構成が改善策として有効です。さらに、具体的にどの画面をどう変更するのか、誰がいつ対応するのかといった実行計画まで落とし込みます。
施策ごとに「すぐ対応できるもの」「検証が必要なもの」などを分けておけば、UX改善の取り組みが効率的かつ着実に進行できます。
ユーザーシナリオを作る4つのメリット
ユーザーシナリオは、単にユーザーの行動を描くだけのツールではありません。ここでは、ユーザーシナリオを作成すると得られる主なメリットを4つ紹介します。
- ユーザーの行動全体を一目で把握できる
- 潜在ニーズや感情を見つけやすくなる
- 課題や改善点を明確にできる
- チーム全体でユーザー理解を共有できる
1.ユーザーの行動全体を一目で把握できる
ユーザーの行動を最初から最後までストーリーとして整理すると、体験の全体像が明確になり、つまずきやすい場面や改善の余地がある接点を把握しやすくなります。
例えば、学習アプリのユーザーシナリオでは「アプリを開いて教材を選ぶ→勉強を始める→成果を確認する」といった流れを時系列で整理できます。これにより、途中で離脱しやすい工程や、改善すべき操作フローが明らかになります。
2.潜在ニーズや感情を見つけやすくなる
ユーザーの行動とともに感情や心理も描くと、普段は見落としがちなニーズや期待を発見できます。表面的な行動だけでなく、その背後にある「なぜその行動を取ったのか」に注目することで、より深いユーザー理解が得られるのです。
例えば「繰り返し検索する」「途中で戻る」といった行動があれば、情報が見つからないことに苛立ちや不安が存在する可能性があります。ユーザーシナリオを丁寧に描けば潜在的な課題が可視化されるため、課題解決に向けた改善や提案につなげられます。
3.課題や改善点を明確にできる
ユーザーの動きと心理を時系列で追うと、サービス上の課題や改善ポイントが明確になります。どこに課題が潜んでいるかを具体的に見極めやすくなり、改善の優先度も判断しやすくなります。
例えば、あるページでユーザーの離脱が多い場合、その直前の心理状態や表示内容に問題があるかもしれません。ユーザーが不満を感じた要因を明確にし具体的な対応策を講じると、改善の効果を高められます。
4.チーム全体でユーザー理解を共有できる
ユーザーシナリオは、開発・デザイン・マーケティングなど、異なる担当者間で共通認識を持つための資料としても有効です。抽象的なユーザー像ではなく、具体的な行動や感情を描いたシナリオがあるとプロジェクト全体の意思統一が図りやすくなります。
例えば、開発チームは機能改善の優先度を把握しやすくなり、デザインチームはUIや導線設計の意図を理解できます。チーム全体が同じ視点でユーザー体験を考えることにより、施策の一貫性が生まれ、ユーザーにとっても価値のある体験を提供しやすくなります。
まとめ
ユーザーシナリオは、UX改善やサービス設計における基礎となるフレームです。ユーザーの行動や心理を具体的に描き出すことで課題の発見、改善策の立案、チーム内の共通認識の醸成など、さまざまな場面で活用できます。
特に近年は、ユーザーの感情や背景を踏まえた体験設計が重視されており、ユーザーシナリオの重要性はますます高まっています。準備・描写・改善という3つのプロセスを丁寧に進めると、より信頼性のあるシナリオを作成できるはずです。
ぜひ実践に取り入れて、ユーザーに寄り添ったサービスづくりを進めてみてください。


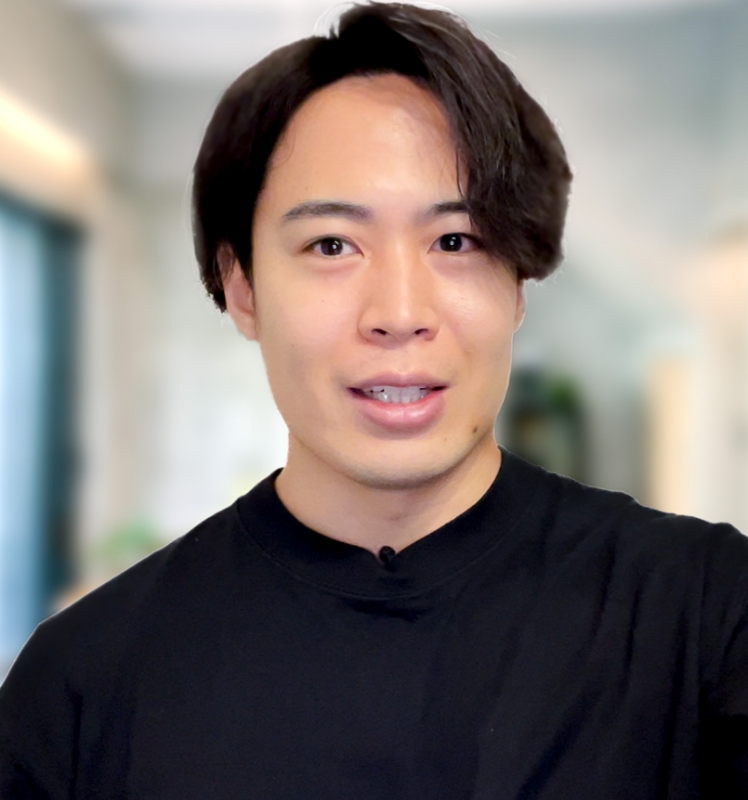

につなげる戦略的な導線設計-.png)



の改善策11選!当社の成功例を交えて解説.png)