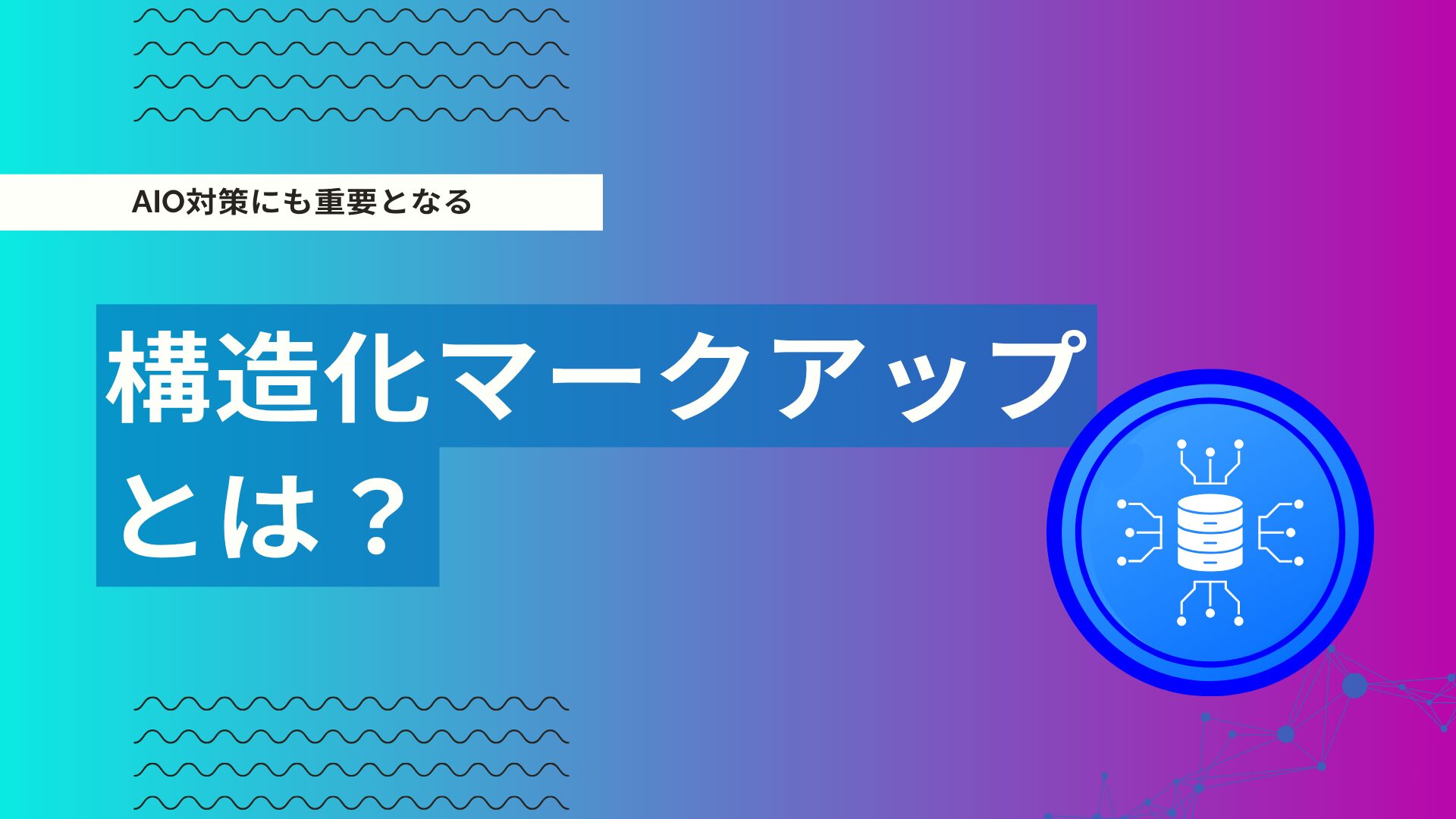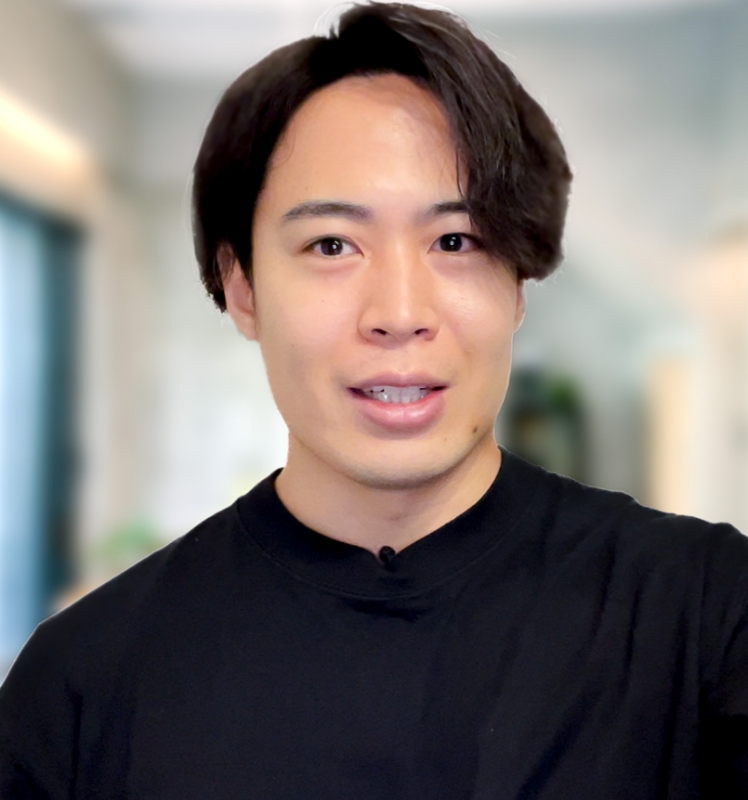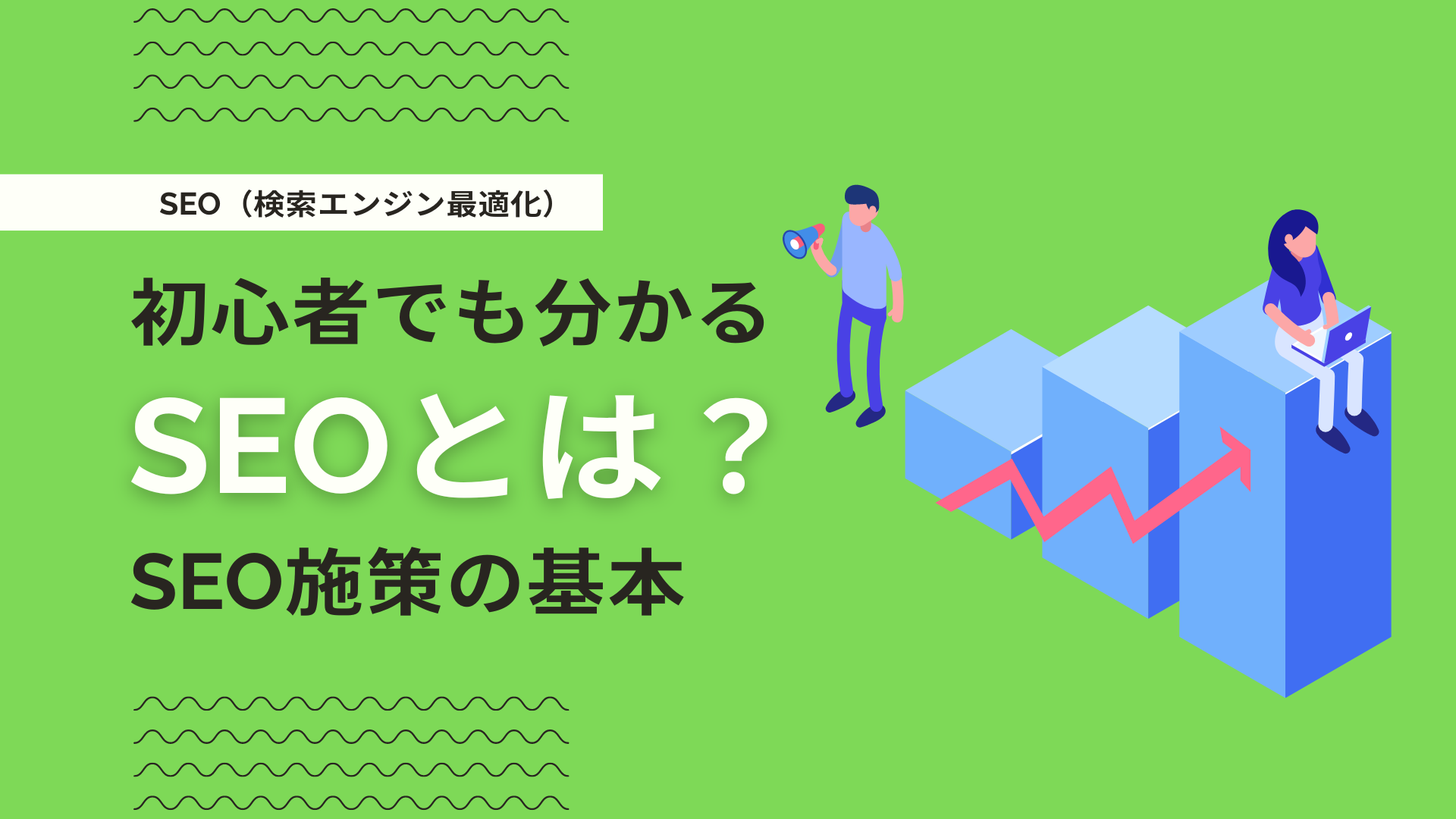この記事でおさえておきたいポイントは以下です。
- 構造化データとは?
-
検索エンジンがページの内容を正確に理解するための「共通言語」が構造化データです。GoogleやLLMは、テキストを読むだけではなく、その文脈や意図を理解するために構造化された情報を参照します。
- 構造化データをマークアップすることによるSEO効果とは?
-
構造化データを適切に導入すると、Google検索におけるCTR向上やサイトの信頼性強化が期待できます。また、AI検索(SGE・Geminiなど)でも引用・理解されやすくなり、SEOとAIO(AI最適化)の両面に効果を発揮します。
- 構造化マークアップの有無について確認方法は?
-
Google公式ツールで検証が可能です。おすすめのツールは以下の2つです。
構造化データとは、Webページの内容を検索エンジンが理解しやすくするために、特定の形式で記述するデータのことです
GoogleやAIがページ内容を正しく認識し、検索結果で「リッチリザルト(星評価・FAQ・イベント情報など)」として表示される効果があります。また、この構造化データを設置することで、LLM(大規模言語モデル)がWebページの内容を正確に理解することができるため、LLMO対策の一環としても注目されています。
この記事では、構造化データの仕組み・SEO効果・設定方法をわかりやすく解説します。
COOMIL(クーミル)株式会社 代表取締役。神奈川県出身。東京薬科大学大学院を修了後、大手製薬会社にて研修開発に従事する。2016年にファングロウス株式会社を創業し、マーケティング、広告運用、YouTube、SEO対策を駆使し、2年で売上1億円強かつ利益率40%強の会社へとグロースさせ、株式譲渡。YouTubeチャンネルのプロデュース・原稿制作・出演・撮影・編集の全てを自ら行い、運営10ヶ月で登録者数1万人突破させる(現在3万人越え)。IT業界だけでなく実店舗経営の知見を活かし、クライアント様の課題の本質を捉えて、「結果が出るマーケティング施策」をご提案致します。サイトを公開後も運用をお任せ頂き、サイトだけでなく「事業規模の拡大を目指す」ことがクーミルのモットーです。
■経歴
2014年 東京薬科大学大学院終了
2014年 第一三共株式会社
2016年 ファングロウス株式会社 創業
2019年 一般社団法人スーパースカルプ発毛協会(FC本部) 理事
2021年 ファングロウス株式会社 株式譲渡
2021年クーミル株式会社 創業
■得意領域
SEO対策
コンテンツマーケティング
リスティング広告
オウンドメディア運用
フランチャイズ加盟店開発、集客
■保有資格
Google アナリティクス認定資格(GAIQ)
Google 広告検索認定資格
Google 広告ディスプレイ認定資格
Google 広告モバイル認定資格
■SNS
X(旧Twitter):https://twitter.com/ryosuke_coomil
YouTube:https://www.youtube.com/@marketing_coomil
お悩みを無料で相談する
Step1
ありがとうございます
弊社にご相談頂きまして
誠にありがとうございます。
クーミル株式会社では、
1つ1つのご相談を真剣に考え、
最適解をご提供出来るよう日々努めております。
可能な限り、即日ご返信を心掛けておりますが、
相談内容や、
営業日の関係で少々、
お待たせさせてしまうかも知れません…。
目次
- 構造化データとは?その意味と役割
- 構造化データの定義と仕組み
- Googleが構造化データを重視する理由
- 構造化データと非構造化データとの違い(表)
- 構造化データがSEOにもたらす効果
- リッチリザルト表示によるクリック率(CTR)改善
- E-E-A-T・ナレッジグラフへの寄与
- FAQ・レビュー・記事スキーマの活用法
- LMと構造化データの関係性
- LLMはどのようにWeb情報を理解しているか
- クエリファンアウトと構造化データの相互作用
- AI時代における構造化データの重要性
- AI検索(SGE・Perplexityなど)で構造化情報が使われる理由
- LLMが「意味理解」に利用する構造化コンテキスト
- AIに“引用される”コンテンツ設計のポイント
- 構造化データの基本実装と最適化手順
- SON-LD形式での記述例(Article/FAQ/HowTo)
- 構造化データの検証ツールとエラー対処
- AI理解を強化するスキーマ設計(Article+Author+Organization)
- 構造化データの今後の有用性について
- SEOからAIOへ──AIに評価される時代の到来
- AIに読み取られる「文脈構造」とは?
- まとめ|LLMに理解されるWebサイトをつくるために
構造化データとは?その意味と役割
検索エンジンがページの内容を正確に理解するための「共通言語」が構造化データです。GoogleやLLMは、テキストを読むだけではなく、その文脈や意図を理解するために構造化された情報を参照します。
構造化データの定義と仕組み
構造化データとは、Webページの内容(記事・商品・FAQなど)を機械が理解できる形式(Schema.orgなど)で記述したデータです。GoogleはHTML構造だけでなく、このデータを参照してページの意味を判断します。
例:ArticleスキーマのJSON-LD
{
"@context": "https://schema.org",
"@type": "Article",
"headline": "構造化データとは?LLM時代のSEOとAI最適化の関係を徹底解説",
"author": { "@type": "Person", "name": "馬鳥 亮佑" },
"publisher": { "@type": "Organization", "name": "クーミル株式会社" }
}
このように、「対象ページは記事であること」「著者は誰か」「どの企業が発信しているか」を明示することで、検索・AI双方の理解が格段に向上します。
Googleが構造化データを重視する理由
Googleは近年、検索結果を単なるリンクリストではなく「意味的な回答」として進化させています。構造化データは、AIがページ内容を正確に要約・分類・ランキングするための基盤としても使われています。
- Web情報を統一的に理解しやすくする
- 検索結果でリッチリザルト(星・FAQ・イベントなど)を表示
- AI検索・SGE・Google for Jobsなどの新機能に対応
構造化データを実装することで、SEO効果だけでなくAI時代の露出機会が増やすことができます。
構造化データと非構造化データとの違い(表)
非構造化データ(例:通常のHTMLテキストや画像)は、人間には読めてもAIには文脈を理解しにくい情報です。対して構造化データは「意味付きデータ」であり、誰が・何を・どう伝えているかを形式化します。
| 比較項目 | 非構造化データ | 構造化データ |
|---|---|---|
| 内容理解 | 難しい | 容易(明示的) |
| データ形式 | HTML・テキスト | JSON-LDなど |
| SEO効果 | 通常評価 | リッチ表示・AI最適化 |
| 検索エンジン対応 | 制限あり | 優先評価対象 |
構造化データは、AIに“読みやすい言語”で情報を伝える仕組みといえます。LLMからの引用や参照率を高める上でも構造化データの実装は必須と言えるでしょう。
構造化データがSEOにもたらす効果
構造化データを適切に導入すると、Google検索におけるCTR向上やサイトの信頼性強化が期待できます。また、AI検索(SGE・Geminiなど)でも引用・理解されやすくなり、SEOとAIO(AI最適化)の両面に効果を発揮します。
リッチリザルト表示によるクリック率(CTR)改善
構造化データを導入すると、検索結果にレビュー・FAQ・イベント情報などが表示され、他サイトよりも目立ちます。
これがCTRの上昇につながります。
| タイプ | 表示例 | 効果 |
|---|---|---|
| FAQスキーマ | 質問・回答が展開表示 | CTR+10〜20% |
| Reviewスキーマ | ★評価+レビュー数 | 信頼性UP |
| Productスキーマ | 価格・在庫を表示 | CVR向上 |
視覚的訴求と情報の明確化により、検索流入が安定して増加します。
構造化データの種類とページタイプ
| スキーマタイプ | 表示内容 | 適用例 |
|---|---|---|
| FAQPage | 検索結果内で質問と回答が展開表示 | 採用ページ・商品説明ページ |
| Review / AggregateRating | ★評価・レビュー件数が表示 | ECサイト・講座・サービス紹介 |
| Product | 商品名・価格・在庫・画像 | ECサイト・物販サービス |
| Article / NewsArticle | サムネイル・発行日・著者情報 | ブログ・オウンドメディア |
| HowTo | 手順や手法がステップ付きで表示 | 解説記事・マニュアル |
| Event | イベント名・開催日・場所 | セミナー・展示会・ライブ情報 |
| Recipe | 材料・調理時間・カロリー | 飲食・レシピサイト |
| JobPosting | 求人情報(職種・勤務地・給与) | 採用サイト |
| VideoObject | サムネイル・再生時間 | セミナー動画・製品紹介 |
| BreadcrumbList | パンくずリスト | 全ページ共通 |
| Organization / Person | 企業・著者・代表者情報 | 会社概要・ブログ著者欄 |
| Course | コース名・受講時間・費用 | 教育・スクールサイト |
| SoftwareApplication | ソフト・アプリ情報 | SaaS・アプリ紹介サイト |
ページタイプごとに最適な構造化マークアップを実装することで、検索エンジンやLLMからのサイト認識度合いを高めることが可能です。
E-E-A-T・ナレッジグラフへの寄与
Googleの評価基準であるE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)は、構造化データによって強化できます。著者情報や企業情報をスキーマで明示することで、Googleのナレッジグラフに登録され、ブランド認知が向上します。
Personスキーマで著者プロフィールを明記Organizationスキーマで会社情報を統合
結果として、AIやGoogleが「誰が言っているか」を信頼できる形で認識します。
FAQ・レビュー・記事スキーマの活用法
構造化データは記事やFAQページで特に有効です。FAQスキーマを活用すれば、検索画面上で回答が表示され、ユーザー体験を高めつつSEOにも貢献します。
効果的な利用例
- 採用サイト → FAQで「応募条件」「福利厚生」などを明示
- ECサイト → Reviewスキーマ及びProductスキーマで口コミや製品情報を表示
- オウンドメディア → Articleスキーマ及びFAQスキーマを実装
こうした構造的情報は、AIが回答を引用する際の根拠としても利用されます。
LMと構造化データの関係性
ChatGPTやGeminiなどのLLM(大規模言語モデル)は、構造化データを「文脈理解の手がかり」として利用しています。つまり、構造化データはAIが人間の知識を正確に再現するための座標軸なのです。
クーミルでは、LLMOコンサルティングのみならず、実行支援まで一貫して対応可能です。Web制作会社だからこそAIフレンドリーなサイト構造へ改修することも可能です。
LLMはどのようにWeb情報を理解しているか
LLMは単語の並びを統計的に処理するだけでなく、構造化された情報(スキーマ)を参照して意味関係を学習します。特に、Article・FAQ・Organization・Personなどのスキーマは、AIの「知識整理」に直結しています。
- Webクローラーが構造化データを収集
- LLMがスキーマを概念化し、関係性をマッピング
- クエリ(質問)に応じて、関連構造から知識を再構築
つまり構造化データは、LLMがこのWebサイトにどんな情報が記載されているか理解する上で非常に有効となります。
クエリファンアウトと構造化データの相互作用
AIがユーザーの質問を複数のサブクエリに展開する(クエリファンアウト)際、どのページを参照するかを判断する根拠の一つが構造化データです。
クエリファンアウトについて詳しく知りたい人は以下の記事を参考にしてください。

イメージ
ユーザーの質問
↓(分解)
サブクエリ①:定義(Articleスキーマなど)
サブクエリ②:使い方(Howtoスキーマ)
サブクエリ③:事例(Organizationスキーマなど)
↓(AI検索)
構造化データがあるページを優先抽出
つまり、構造化データを適切に設定しておくと、AIが自社ページを「回答候補」や「引用対象」として選びやすくなるのです。
AI時代における構造化データの重要性
AIが検索エンジンの中心となる今、構造化データは単なるSEO施策ではなく「AIとの対話基盤」となっています。ChatGPTやPerplexity、GeminiなどのLLMは、構造化データを“文脈理解のポイント”として利用し、Webの情報を意味的に整理しています。
AI検索(SGE・Perplexityなど)で構造化情報が使われる理由
AI検索は、クエリに対する回答を直接生成する際に「どの情報が信頼できるか」を判断する必要があります。
構造化データはその根拠を明示するため、SGE(Search Generative Experience)やPerplexityなどの生成検索で利用されています。
Articleスキーマ:記事の発行元・著者・更新日をAIが認識FAQPageスキーマ:質問応答形式をそのままAI回答に転用Organizationスキーマ:企業名や公式URLを根拠リンクとして引用
AIはこれらをもとに「どの情報が一次情報であるか」を判断し、信頼性の高い出典を優先的に引用します。
LLMが「意味理解」に利用する構造化コンテキスト
LLMは、文章をそのまま読んでいるわけではなく、内部で「意味ネットワーク」を構築しています。構造化データはそのネットワークに“ラベル”を付ける役割を果たします。
例:FAQスキーマ
{
"@type": "Question",
"name": "構造化データとは何ですか?",
"acceptedAnswer": { "@type": "Answer", "text": "検索エンジンが理解しやすい形式で記述したデータです。" }
}
AIはこの情報を「質問→回答」という構造として学習します。このようなデータはAIにとって“意味の単位”として扱われるため、検索・要約・引用のすべてで優位に働きます。
AIに“引用される”コンテンツ設計のポイント
AIがWebから情報を引用する際に注目しているのは、「構造」「信頼性」「一貫性」の3点です。単に内容が優れているだけではなく、AIが再利用しやすい形式で提示されているかが重要です。
AI引用されやすいページ設計
| 要素 | 具体的な施策 | 効果 |
|---|---|---|
| 情報構造 | H2・H3構成を明確化/FAQを設置 | クエリファンアウト対応 |
| 構造化データ | Article/FAQ/Organizationスキーマを設定 | AIが内容を正確に理解 |
| 出典・著者情報 | 著者名・監修者・企業情報の明示 | 信頼性評価(E-E-A-T)向上 |
| 内部リンク | 関連テーマ・定義ページを相互リンク | ナレッジグラフ形成 |
AIに選ばれるページとは、単なる「検索上位」ではなく、「回答のソース」として信頼される構造を持つページです。
構造化データの基本実装と最適化手順
構造化データを導入する際は、「何を伝えたいか」に応じてスキーマタイプを選び、正しい形式で記述することが重要です。
Googleなどの検索エンジンはJSON-LD形式を推奨しており、タグマネージャーなどでも簡単に設定できます。
SON-LD形式での記述例(Article/FAQ/HowTo)
Articleスキーマ例
{
"@context": "https://coomil.co.jp/",
"@type": "Article",
"headline": "構造化データとは?",
"author": { "@type": "Person", "name": "馬鳥亮佑" },
"publisher": { "@type": "Organization", "name": "クーミル株式会社" },
"datePublished": "2025-10-17"
}
FAQスキーマ例
{
"@context": "https://coomil.co.jp/コラム記事のURL",
"@type": "FAQPage",
"mainEntity": [{
"@type": "Question",
"name": "構造化データはSEOに効果がありますか?",
"acceptedAnswer": {
"@type": "Answer",
"text": "はい。検索結果にリッチリザルトを表示させることでCTRが向上します。"
}
}]
}
HowToスキーマ例
{
"@context": "https://coomil.co.jp/コラム記事のURL",
"@type": "HowTo",
"name": "構造化データの設定手順",
"step": [
{ "@type": "HowToStep", "text": "JSON-LD形式でスキーマを作成する" },
{ "@type": "HowToStep", "text": "Googleのリッチリザルトテストで検証" }
]
}これらを正しく導入すれば、Google・AI検索の双方がページの目的を正確に把握できます。
構造化データの検証ツールとエラー対処
構造化データを導入したら、必ずGoogle公式ツールで検証を行いましょう。
よくあるエラーと対処
| エラー内容 | 原因 | 対策 |
|---|---|---|
| “Missing field” | 必須項目が未入力 | headline, author, publisherを追加 |
| “Invalid type” | スキーマの型が誤り | 対応するスキーマタイプを確認 |
| “Out of scope” | 不適切な組み合わせ | FAQとArticleの混在を避ける |
適切にエラーを修正することで、GoogleインデックスとAI認識の精度が大幅に改善します。
AI理解を強化するスキーマ設計(Article+Author+Organization)
LLMは「誰が・どこから発信している情報か」を構造的に理解します。そのため、Article に Author と Organization を関連付ける設計が推奨されます。
関係構造の例
Organization(Coomil Inc.)
└─ Article(構造化データとは?)
└─ Author(山田太郎/SEOコンサルタント)
このように階層的にスキーマを組むことで、AIやGoogleのナレッジグラフ内で「企業→著者→記事」の信頼ループが形成されます。
構造化データの今後の有用性について
クーミルでは、構造化データは、SEOだけでなくAIO(AI Optimization)における基礎となる対策の一つであると考えています。
現在のAI技術の進歩を考えていくと、検索行動の主流がググるからAIで「引用する」「要約する」「推薦する」時代になる未来はそう遠くないです。そのため、今の段階から構造化データを設置するようにしましょう。
SEOからAIOへ──AIに評価される時代の到来
これまでのSEOは「キーワード対策」中心でしたが、AI検索では「情報の意味と関係性」が評価されます。構造化データを整備することは、AIのクエリファンアウト構造に最適化することを意味します。
| 時代 | 主な最適化対象 | 成功指標 |
|---|---|---|
| 旧SEO時代 | クローラー(Googlebot) | 検索順位・CTR |
| 現在(AIO時代) | AI(LLM・RAG) | 引用率・回答採用率 |
AIに読み取られる「文脈構造」とは?
AIは単語の羅列ではなく「意味のネットワーク(semantic graph)」を読み取ります。構造化データを正しく設計すれば、AIがページ全体を知識ノードとして扱い、他ページとの関係を理解します。
強い文脈構造の条件
- 見出し階層(H2/H3)の一貫性
- 関連ページへの内部リンク(相互参照)
- Schemaでの明示的関係(sameAs, relatedTo)
- FAQ形式での論理的Q→A構造
これにより、AIが回答生成時にページを部分引用しやすくなり、露出率が上がります。
まとめ|LLMに理解されるWebサイトをつくるために
構造化データは、AIに「このページが何を伝えているか」を理解させるための言語です。SEOの延長ではなく、AI時代の情報設計の基礎インフラとして機能します。
LLMが普及する今こそ、構造化データを整備し、“AIに選ばれるサイト”へと進化させることが求められています。